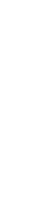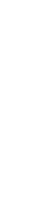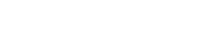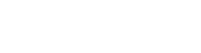【中小企業白書2025年度版-事例紹介⑱】組織を変える診断士的思考
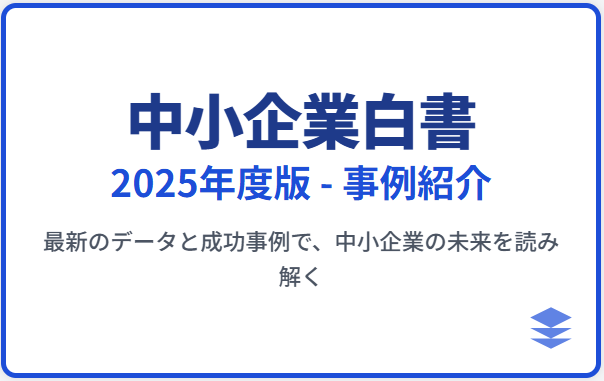

はじめに
中小企業診断士を目指す皆さんにとって、理論だけでなく「リアルな企業事例」から学ぶことは、実務力を高める重要なステップです。2025年度版中小企業白書に掲載された愛知県の金属製品製造業・側島製罐株式会社の事例は、まさに診断士的な視点が活かされている好例です。
変革の原点
側島製罐は、創業100年を超える老舗ながら、近年は赤字が続き、組織の停滞感が課題でした。そんな中、2020年に家業へ戻った石川代表がまず着手したのが「組織の見える化」でした。社内に経営理念すら存在しない状況に危機感を抱き、変革の一歩としてMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)の策定を主導します。
中小企業診断士試験の一次科目「企業経営理論」では、理念経営や組織行動論の重要性が強調されています。まさにこの事例では、その理論が実践に移され、成果につながったのです。
社員主導のMVV
MVVの策定は、トップダウンではなく、社員自らが「自分たちの言葉」で作り上げるプロセスが取られました。石川代表はあくまでファシリテーターとして関わり、オーナーシップは社員に持たせることで、組織の当事者意識を高めました。
このプロセスは、中小企業診断士が支援する「理念浸透」や「組織開発支援」と非常に親和性が高いテーマです。診断士試験でも近年「従業員の自律性」や「エンゲージメント向上」が重要なキーワードとして出題されています。
人事制度の再構築
MVVの策定後、石川代表は人事制度改革に着手。役職制度の廃止、報酬自己申告制の導入など、従来の制度から脱却し、社員一人ひとりが「自ら考え、行動する」組織への転換が図られました。
ここでも診断士試験の「人事労務管理」「組織論」で扱われるフラット型組織や自己決定理論が応用されており、知識が現場でどう活かされるかを実感できる事例です。
業績のV字回復
MVV策定と人事制度改革の成果は数字にも表れました。赤字続きだった同社が、2021年以降3期連続の増収に転じたのです。缶の魅力を活かした新商品や、低CO2素材を使った製品など、社員発のイノベーションが次々と実現されました。
「経営資源の再配置」や「技術と市場のマッチング」といった視点も、中小企業診断士試験の「経営戦略」や「運営管理」で問われる重要項目です。実際の現場で、これらの知識が企業変革の一翼を担っているのです。
中小企業診断士として
この事例を通じて改めて感じるのは、中小企業診断士が学ぶ内容は、単なる理論にとどまらず、現実の経営課題に対する解決力を育てるためのものであるということです。
MVV策定のファシリテーション、組織のエンゲージメント改善、人事制度改革、事業承継支援など、すべてが診断士の専門領域。まさに「経営のかかりつけ医」としての診断士が求められる時代なのです。
学びの現場へ
KEC中小企業診断士講座では、このようなリアルな事例に即したカリキュラムを用意しています。一次試験で得た知識を、実務補習や実務従事にどう結び付けていくか。その先には、企業の変革を支えるプロフェッショナルとしての未来があります。
あなたも、診断士の学びを通して「企業変革の立役者」になってみませんか?
KEC中小企業診断士講座マネージャー佐野
引用:中小企業白書2025年度版