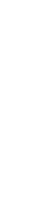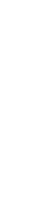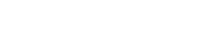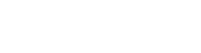【中小企業白書2025年度版-事例紹介㉑】育成で未来を切り拓く企業
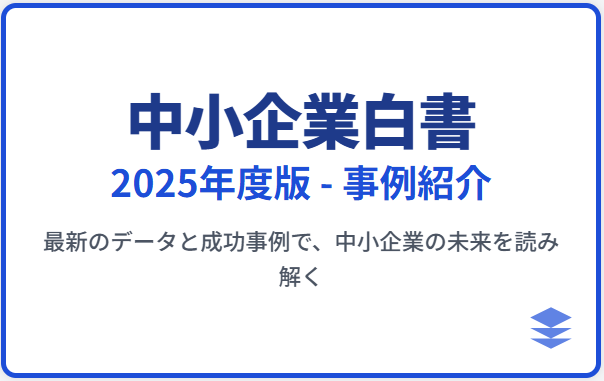

はじめに
中小企業診断士試験では、「人材戦略」「経営戦略」「地域活性化」など多くの重要テーマを学びます。こうした理論が、実際の企業経営でどう活かされているのかを知ることは、受験を検討されている方々にとって大きなヒントになります。今回は、高知県のIT企業・四国情報管理センター株式会社の事例から、人材育成と地域貢献に向けた取り組みを紹介します。
人材確保の課題
情報サービス業にとって、ITスキルを持つ人材の確保は大きな経営課題です。とりわけ地方都市に本社を構える企業にとっては、大都市圏への人材流出が深刻です。四国情報管理センターも例外ではなく、未経験人材の採用と育成を戦略的に進めてきました。
これは中小企業診断士試験で学ぶ「経営資源の確保と活用」、特に人的資源の戦略的活用の重要性を示す実例です。
10か月の研修
未経験者の採用に際して、同社では10か月におよぶ研修プログラムを構築。基礎研修からOJT、さらに高度スキル研修へと段階的にスキルアップを図る制度を整えています。これは単なる研修を超え、「職場へのスムーズな定着」や「将来の中核人材育成」を意識した仕組みです。
このようなアプローチは、中小企業診断士の「人事労務管理」や「組織論」で学ぶ人材開発の典型例といえます。
全社で学ぶ
同社ではIT部門だけでなく、営業・総務職を含む全社員を対象にした「学習コンペ」も実施。社員をチームに分けて資格取得を競い合い、表彰制度を設けることで、組織全体の学習意欲を高めています。これはインセンティブ設計と組織活性化の好例です。
診断士試験で登場する「モチベーション理論」「人材評価制度の設計」といった内容が、現実の人材戦略にどう結びつくかを示す興味深い取り組みです。
地域貢献と成長
研修や育成にとどまらず、同社は地域課題の解決にも積極的です。たとえば農産品直販所の販売状況の可視化や、地域の行政支援システムの構築など、ITの力で地域の課題に取り組む姿勢は、社員の「仕事への誇り」と「やりがい」を育てる効果も持っています。
「中小企業政策」や「地域経済論」で学ぶ知識が、まさに現場で活かされる好事例といえるでしょう。
成果と定着率
このような人材投資は確かな成果を生んでいます。高度資格取得者の増加、離職率の低下(2023年度はわずか2.7%)、そしてUターン・Iターン希望者の増加といった形で表れています。人材育成と社会課題解決の両立が企業の持続的成長に直結していることがわかります。
診断士として企業支援に関わる際、こうした成功事例の知見は非常に貴重です。
診断士の視点
人材不足や地方企業の成長課題に対して、中小企業診断士としてできることは数多くあります。採用戦略、人材育成、地域連携、事業展開の提案など、多岐にわたる視点が求められるからこそ、診断士としての学びが活かされるのです。
KEC中小企業診断士講座では、こうしたリアルな現場の課題解決につながる知識を体系的に学べます。あなたの学びが、地域と企業を元気にする力になります。
KEC中小企業診断士講座マネージャー佐野
引用:中小企業白書2025年度版