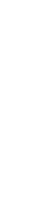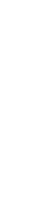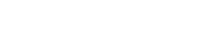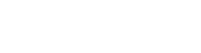【中小企業白書2025年度版-事例紹介⑫】GX推進が生んだV字回復
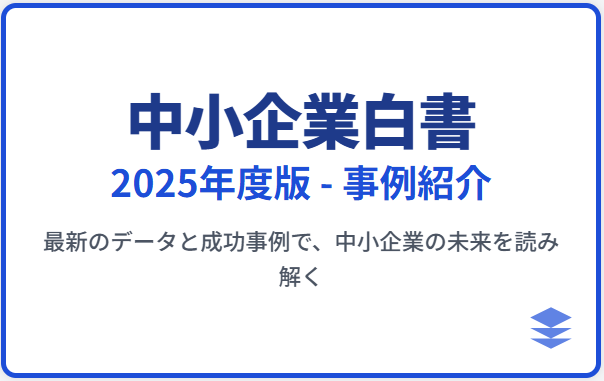

中小企業白書2025年度版では、GX(グリーントランスフォーメーション)への挑戦が企業の成長戦略に直結している事例が多数紹介されています。今回はその中から、岡山県の金属製品製造企業「備前発条株式会社」の取組に注目し、中小企業診断士としての視点でどのように学びや分析が活かせるのかをご紹介します。
危機が変革の契機
備前発条株式会社は、創業以来70年を超える老舗の製造業です。自動車部品を主力とする同社は、2019年に世代交代を迎えた直後、コロナ禍による操業停止という大きな打撃を受けました。この混乱の中、欧米諸国の環境意識の高まりや、IT企業による脱炭素調達方針に触れたことが、GXへの取組の第一歩となります。
ここで重要なのは、「経営環境の変化をどう読み解くか」です。中小企業診断士試験の〈経営環境分析〉では、PEST分析などを通じて外部環境の変化を予測・分析する手法を学びます。この事例は、まさにその理論の実践例と言えるでしょう。
社内巻き込み力
2023年、備前発条は「SDGsチーム」を結成し、部署横断でGX推進を進めます。これは単なるCSR活動ではなく、CO2削減を「経営目標」として明文化することで、全社的な行動変容を引き出した点が特筆に値します。
中小企業診断士として現場に入る際、「組織活性化」や「プロジェクト推進」に関する知見が問われます。診断士試験で学ぶ〈組織論〉〈人事・労務管理〉の知識が、こうした改革の支援や、社内の巻き込み戦略に活かされます。
数字で語る成果
同社はLED照明や塗装プラントの高効率化、CO2フリー電力導入など、実行可能な施策を積み上げ、2023年には約19トン、2024年には127トンのCO2削減を達成。さらに、売上高あたりのCO2排出量は2019年比で34%減という成果を記録しました。
これは「定量目標によるマネジメント」の好例です。診断士試験で扱う〈財務・会計〉の知識を用いれば、「投資対効果」「炭素強度」「コスト削減」など、企業価値と環境対応の両立を可視化する力が身につきます。
自発性が生む連鎖
GX取組が評価され、2024年度には5名の採用を実現。さらに既存・新規の取引先からの信頼を得て、売上は2020年度の26億円から2024年度には過去最高の35億円へとV字回復を遂げました。
ここで注目したいのが「従業員の自発性」と「情報発信力」です。診断士が支援する現場では、制度導入や補助金活用だけでなく、社員の意識をどう醸成し、外部にどう伝えるかが成果を左右します。これは〈マーケティング〉や〈経営戦略論〉で学ぶ知識の実践そのものです。
資格学習の価値
中小企業白書で取り上げられる企業事例は、机上の空論ではなく、現場の課題に即したリアルな知見の宝庫です。中小企業診断士の学びは、こうした変革の道筋を理論的に支え、数値化し、再現可能な仕組みとして提案できる力を育てます。
KEC中小企業診断士講座では、こうした事例をもとにした実践的な講義を通じて、GX、SDGs、地域企業の経営革新といった最新トピックにも対応したカリキュラムを提供しています。
まとめ
備前発条株式会社の事例は、「危機をチャンスに変える経営判断」と「社内外を巻き込むGX推進力」を示す好例でした。中小企業診断士を目指す皆さんにとって、経営環境の変化を読み解き、変革を支援する視点を持つことの大切さを、ぜひ本事例から学び取っていただきたいと思います。
KEC中小企業診断士講座マネージャー佐野
引用:中小企業白書2025年度版