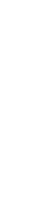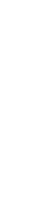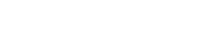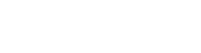【中小企業白書2025年度版-事例紹介⑲】経営管理で企業成長を実現
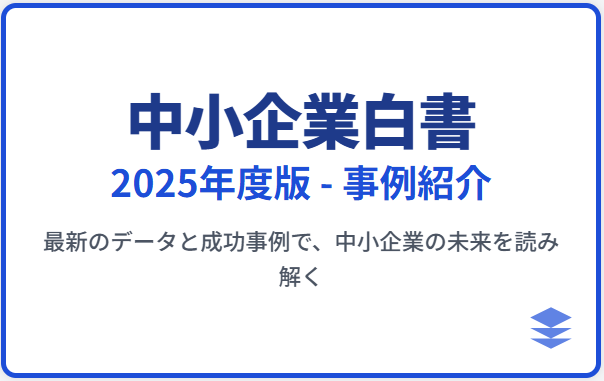

はじめに
中小企業診断士を目指す皆さんにとって、試験科目で学ぶ理論が「実際の経営の現場」でどのように活用されているかを知ることは、モチベーションにも直結する重要なポイントです。今回は中小企業白書2025年度版に掲載された、千葉県の株式会社食研の取り組みを紹介しながら、診断士としての視点で解説していきます。
課題の発見
株式会社食研は、食肉加工品や冷凍食品を扱う製造業者で、2023年度の売上高は2010年度比で約2.5倍に達しています。一見すると順風満帆な成長企業に見えますが、急成長の裏では「経営管理の大雑把さ」や「業務の属人化」といった課題が山積していました。 これらは中小企業診断士試験の「企業経営理論」や「財務・会計」で学ぶ「管理体制の未整備によるリスク」に該当する典型例です。
管理体制の再構築
新井社長が着目したのは「管理会計」の強化です。従来は財務会計ベースの月次報告しかなかった同社に、リアルタイムの製造原価把握を実現するため、既存の生産管理システムを再活用する方針をとりました。ここで重要となったのが、IT人材の社内育成、従業員向けの管理会計教育、業務マニュアルによる標準化です。
これはまさに診断士試験「運営管理」「情報システム」「中小企業政策」などで学ぶ「IT活用による業務改善」「人材育成と標準化の推進」などの知識が必要とされる場面です。
教育と人材育成
管理会計の定着に向け、新井社長自らが講師を務めた勉強会が千葉市と豊橋市の工場で行われ、限界利益や損益分岐点など、診断士試験でも頻出の管理会計用語が従業員に共有されました。半年かけて実施された教育プログラムによって、従業員の意識が「作業」から「改善・提案」へと進化していきました。
これは診断士が企業支援で取り組む「人材開発支援」に通じるもので、経営者が知識を活かして現場を変革していく好例といえます。
成果の可視化
こうした取組により、同社では製造原価のリアルタイム把握、工場別・製品別の収益性分析が可能となりました。価格交渉の精度が上がり、コスト削減の成果も数値として確認できるようになったことで、従業員のモチベーションも大きく向上。作業の意味を理解したうえで行動する文化が社内に根付いてきました。
この変化は、診断士が学ぶ「経営戦略」や「組織論」での成果指標の重要性を示すものであり、試験での知識が実務で活かされる場面の具体例としても非常に有益です。
未来への投資
さらに同社では、RPAなどの自動化技術を活用した業務の高度化にも取り組んでおり、IT人材育成プロジェクトは継続中です。新井社長は「売上は七難を隠す」と語り、売上だけに頼らず、将来の成長に必要な「無形資産」としての人材・制度への投資を続けています。
これは診断士試験の最重要テーマのひとつである「経営資源の最適配分」や「人的資源戦略の立案」とも深く関わっています。経営を数字と人の両面から捉える診断士の知識が、まさに求められる局面です。
診断士の役割
このような変革の裏には、「現状を可視化し、改善に向けた具体策を導き出す」という診断士の本質的な役割が詰まっています。経営者自身が診断士的思考を身につけることで、組織全体が変わる。まさに、中小企業診断士の知識が「経営の羅針盤」となることを示す好事例です。
KEC中小企業診断士講座では、こうしたリアルな企業事例を教材に取り入れ、知識と実務の架け橋となる学びを提供しています。
KEC中小企業診断士講座マネージャー佐野
引用:中小企業白書2025年度版