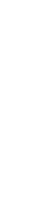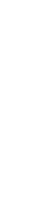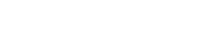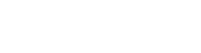【中小企業白書2025年度版-事例紹介⑳】透明経営で組織を変える力
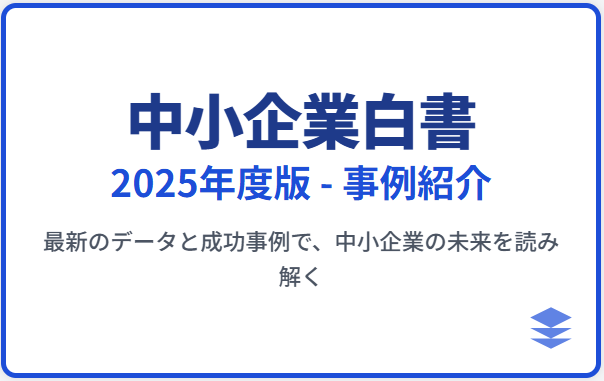
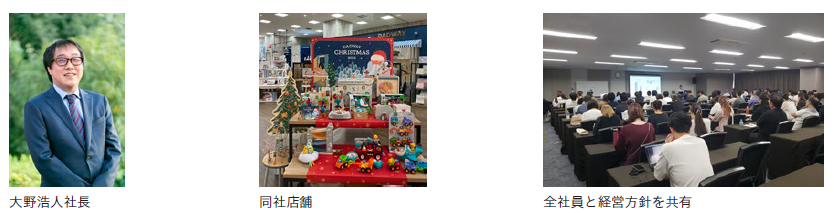
はじめに
中小企業診断士試験では「企業経営理論」や「財務・会計」「中小企業政策」など、多岐にわたる知識を学びます。これらの知識が、実際の企業経営にどのように活かされているかを知ることは、受験を目指す方にとって大きなモチベーションになります。今回ご紹介するのは、神奈川県横浜市の株式会社ダッドウェイの取り組みです。
事業承継と変革
ダッドウェイは、ベビー・キッズ用品の卸売業・小売業を展開する企業です。創業社長から親族外の大野社長への事業承継を経て、持続可能な組織づくりを目指して経営の透明性向上に取り組みました。事業承継を機に企業統治を見直すという姿勢は、中小企業診断士が支援する場面でも非常に多く見られるテーマです。
試験でも「ガバナンス」「組織変革」などが問われることが増えており、まさに実践的な事例といえるでしょう。
外部資本の導入
大野社長はまず、第三者割当増資により東京中小企業投資育成株式会社を外部株主として迎えました。これにより、外部からのチェック機能を強化し、経営のガバナンス体制を整備。社外取締役には財務会計に精通した人材を登用し、取締役会を「経営判断の場」として進化させました。
中小企業診断士試験で学ぶ「コーポレートガバナンス」や「外部経営資源の活用」といった概念がそのまま活用されている点は、受験者にとって非常に参考になるポイントです。
DXと情報開示
組織の透明性向上に向けて、同社はDX(デジタルトランスフォーメーション)を加速。部署ごとにExcelで管理されていた業績データを統合するBIツールを独自開発し、社員がリアルタイムで経営数値を把握できる環境を構築しました。 このような仕組みは、診断士試験の「経営情報システム」や「運営管理」に通じるもので、情報の可視化が組織力の向上に寄与する好例です。
組織活性化の成果
ガバナンス体制の整備と情報共有の促進は、社員のモチベーション向上にもつながりました。データに基づいて自ら提案する社員が増え、業務改善の意識が組織全体に広がっています。部署間で重複していた作業も75%削減されるなど、具体的な成果も出ています。
「人材活用」や「モチベーション理論」など、診断士試験でも頻出のテーマが、こうした組織変革の根幹となっていることがわかります。
診断士の視点
大野社長の言葉に「外部株主や社外取締役の導入は、経営判断に多様な視点を加え、規律と透明性をもたらした」とありますが、これはまさに中小企業診断士が企業に提供すべき価値そのものです。データ分析、ガバナンス強化、人材育成など、診断士が担う役割は広く、今後さらに期待が高まる分野です。
KEC中小企業診断士講座では、こうした現場での実践に活かせる知識を体系的に学べるカリキュラムを提供しています。理論だけでなく、リアルな経営現場を変える力を育てたい方にとって、絶好の学びの場です。
KEC中小企業診断士講座マネージャー佐野
引用:中小企業白書2025年度版