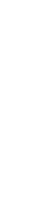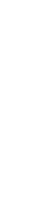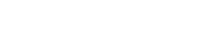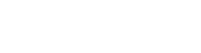【中小企業白書2025年度版-事例紹介㉕】経営者の変革が組織を動かす
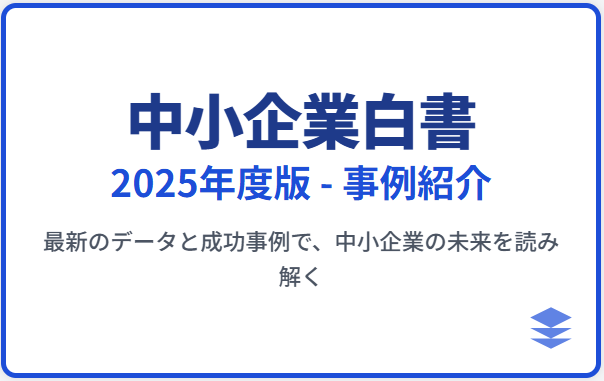

はじめに
中小企業診断士試験では「組織論」「経営戦略」「リーダーシップ」など、経営者の意思決定と組織変革が中心テーマとして登場します。今回は奈良県葛城市の梅乃宿酒造株式会社が、経営者自身の意識変革から始まり、組織全体を巻き込んだ変革に挑戦した事例をご紹介します。まさに診断士で学ぶ理論が実務でどう活きるかを体現する好事例です。
危機感の欠如
吉田社長が就任した2013年当時、老舗酒蔵としての歴史や収益基盤が一定の安心感を与えていたものの、国内酒類需要の減少という市場の変化に対して、社員の危機感は乏しい状況でした。会議の場でも変革の議論は進まず、思うような組織変化が起きなかったといいます。
このような「内的安定」と「外的環境の変化」のギャップこそ、中小企業診断士試験で学ぶ「環境分析」「変革マネジメント」の典型的な出題領域です。
経営者の脱皮
突破口となったのが、社長自身が参加した経営者ネットワークでした。多様な経営者との出会いや情報共有の中で、自らの固定観念を打ち破り、成長への覚悟が芽生えたといいます。これはまさに、診断士が支援する「自己革新型リーダーシップ」の具体化です。
社長は「売上=顧客満足」「利益=価値提供の証」と再定義し、保守的だった中期計画を高い目標に改定。そのメッセージは次第に社員の行動を変え、成長への一体感が醸成されていきました。
社員の変化
社員のマインドも徐々に変わり、「10年後に売上200億円を目指す」といった目標を自ら掲げるようになったことが、その証左です。社内には前向きな発言や提案が増え、組織全体にポジティブな空気が広がっていきました。
これは診断士試験の「組織行動論」や「モチベーション理論」で登場する“心理的オーナーシップ”が浸透した状態といえます。経営者の意識変革は、社員の意識変革を誘発する強力なトリガーとなるのです。
売上と人材
結果として、2024年6月期の売上高は過去最高の30億円に到達。さらに社長の成長姿勢に共感して、大手企業からの転職者も加わり、社内の多様性と活力が高まっています。これは「リーダーシップが企業文化に与える影響」そのものです。
中小企業診断士として「戦略」と「人」をつなぐ視点を持つことが、どれほど重要かがよくわかる事例と言えるでしょう。
診断士の視点
吉田社長は「経営者の覚悟がなければ会社の成長は実現しない」と語っています。そしてその覚悟は、良き経営者仲間や事例との出会いから生まれるといいます。中小企業診断士の学びは、まさにその「良きお手本」を体系化し、理論と実践を結びつけるツールです。
KEC中小企業診断士講座では、こうした実例を教材に取り入れながら、実務にも活かせるカリキュラムを展開しています。学ぶことで、自らも組織も変えられる──それが診断士の価値であり、学ぶことの意義です。
KEC中小企業診断士講座マネージャー佐野
引用:中小企業白書2025年度版